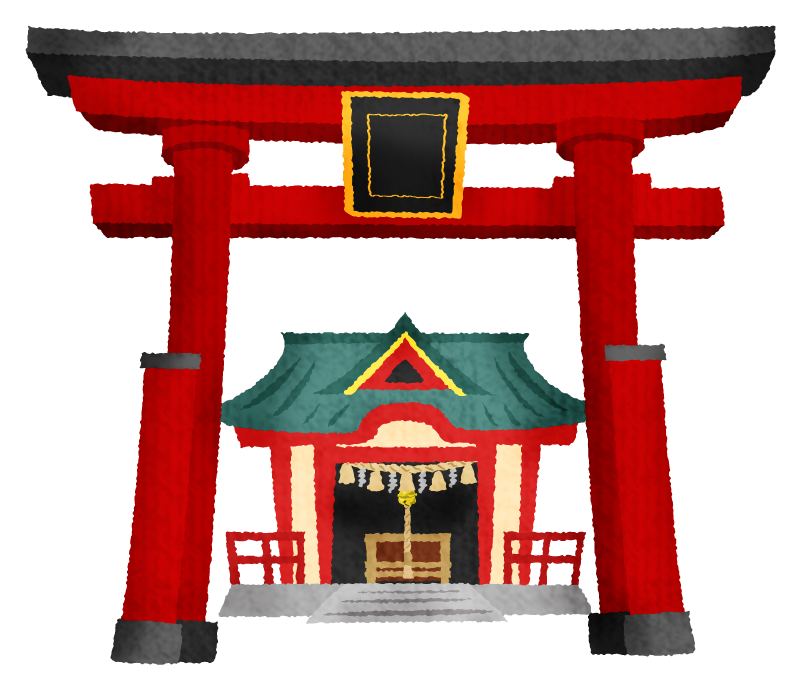【神道(神社)葬儀での作法やマナー】
葬儀は『神葬祭(しんそうさい)』と呼ばれます。突然の訃報にも慌てずに、最低限のマナーは身につけておきたいものですね。
神道の場合、不祝儀袋は白色のシンプルなものを、水引は黒と白の結び切りのものを用意しましょう。
市販されている不祝儀袋の中には、蓮の花など仏教にちなんだ絵柄が入っているものもあるので、十分に注意しましょう。また表書きは『御霊前』『御榊料』『御玉串料』とするのが一般的です。
『御香典』と書くのは仏式だけですので注意しましょう。
葬儀に参列する際の服装は一般的な喪服で問題ありません。ネクタイも黒無地の物が良いでしょう。数珠は神道では使用しません。
〖手水(ちょうず)の作法〗
葬儀の前に参列者の心身を清める大切な儀式です。まず、桶の御神水を柄杓ですくい最初に左手を、続いて右手を三度に分けて洗い流すようにします。次に柄杓を持ち替えて左手水を受け、この水で口をすすぎます。最後に柄杓をもとの場所に戻して懐紙(半紙)で両手をふき取ります。
〖拝礼の作法〗
神道での拝礼は、頭を二回下げ、柏手を二回打ち、最後に一礼する『二礼二拍手一礼』という順番で行うのが一般的です。
但し、葬儀など弔事の柏手は、両手を打つ直前で止めるようにし、音を立てないようにくれぐれも注意しましょう。これを『忍び手』と呼びます。
〖お悔やみの言葉に仏教用語は使わない〗
神道と仏教では『死』に対する考え方が違うため、『冥福』『成仏』『供養』といった仏教用語は使わないように配慮しましょう。
お悔やみの言葉を伝える際は「御霊の平安をお祈りいたします。」や「心より拝礼させていただきます。」などと伝えましょう。
葬儀自体は仏式と同じように通夜にあたる『通夜祭・遷霊祭(せんれいさい)』,葬儀・告別式にあたる『葬場祭』があり、その後『火葬祭』『埋葬祭』『帰家祭』が二日間の日程で執り行われます。参列する際の服装のマナーは仏式と同じように考えて問題ありませんが、お悔やみの言葉として仏教用語は使わないように注意しましょう。
不祝儀袋や表書きも仏式とは異なりますので、注意しましょう。
ここからは、神葬祭の流れについてのお話しです。
【神道の葬儀】
神道の儀式には、長い歴史の中で仏教と相互作用の末に作り上げられた点も多いのですが、その基本にある考え方は大きく異なります。
そのためお葬式や参列の仕方にも違いがあるのです。まずは基本的な作法から押さえておくことをお勧めします。
神葬祭は、仏教の葬儀とはその意味合いが異なる宗教行事です。
仏教の葬儀は『死者の魂を極楽浄土へ送り出すための儀式』であるのに対し、神道の葬儀は『亡くなった家族を先祖と共に守り神として奉る』ことを目的として行われます。
お葬式の会場もご自宅や、セレモニーホールなどを利用することが一般的です。
神道では人間の死を『穢れ』として考えるため、神社などの神聖な場所では葬儀をほとんど行いませんが、神道の儀式を経て死者は神様となり、御神職や家族よりも上位に位置づけられます。
〖神式の葬式の流れ〗
逝去当日
①帰幽奉告(きゆうほうこく)
ご自宅の神棚や祖霊舎(それいしゃ。先祖をまつる祭壇)にご家族が亡くなったことを奉告し、先祖の霊が死者の穢れに触れないよう前面に白紙を貼り付けて封をします。
②枕直しの儀
ご遺体を清め、白小袖を着せて北枕に安置します。小案(小さな台)を2つ設け、一方には故人が日頃好んで口にしていた食べ物(常餞 じょうせん)や、米や酒(生餞 せいせん)を置きます。
もう一方の案には守り刀の背をご遺体に向ける形で配置します。
③〖納棺の儀〗
ご遺体を棺に納め、しめ縄と紙垂(しで)をめぐらせて棺の周りを装飾します。
また、納棺前に故人を白小袖などに着替えさせる場合もあります。
神葬祭一日目
④〖通夜祭〗
神葬祭一日目に行う通夜祭では、神職が祝詞を読み上げ、参列者は榊の枝に紙垂などを結わえた「玉串」を奉奠します。
⑤〖遷霊祭(せんれいさい)〗
通夜祭の次に行うのが、〖遷霊祭〗における御霊写しという儀式です。
神職が故人の霊を、仏葬の位牌に当たる〖霊璽(れいじ。御霊代とも言う)〗に移します。通夜祭でこの儀式の際に一時、式場の電気が消されます。
〖神葬祭二日目〗
⑥〖葬場祭〗
神葬祭二日目の〖葬場祭〗では、仏葬における葬儀や告別式のように弔辞奉読や祝詞奉上などを行います。仏式では焼香を行うのに対し、神式では玉串を奉げます(玉串奉奠)。
⑦〖火葬祭と埋葬祭〗
葬場祭を終えた後は、火葬場で火葬祭を行います。埋葬は五十日祭を目安にすることが習わしとされていますので、お墓に納骨する際に埋葬祭が行われます。
⑧〖帰家祭〗
全てのお葬式の日程を終えたあと、喪家は自宅へ帰って塩と手水で身を清めます。祓除の儀を済ませた後で葬儀でお世話になった神職の方や、世話役の労をねぎらう直会という宴を振る舞います。
神棚は納骨を済ませた後(没日から五十日目)を目安に封印を解くようになります。
【神道形式のお葬式に参列する際のマナー】
神式の葬儀でお参りする際(玉串奉奠の際)は、まず神職に一礼し、神前(玉串案前)に一礼、玉串を供えたあとで拝礼を行います。
拝礼の仕方は、神社に参拝する時と同様〖二礼・二拍手・一礼〗の通りです。ただし弔事であるため、中間の二拍手は音を鳴らさない〖忍び手〗で行うことを覚えておきましょう。
なお、仏葬での香典は神葬祭では〖御玉串料(おんたまぐしりょう)〗〖御榊料(おさかきりょう)〗〖御霊前(ごれいぜん)〗のいずれかを記し、不祝儀袋(香典袋)に納めて渡します。
日本に古くから伝わる神道と仏教では、お葬式の流れにも共通点が多く見られます。
天理教について
〖天理教とは〗
天理教とは幕末に民間で発生した神道教団の一つで、神仏習合の創唱宗教です。神道十三派のひとつになっています。
奈良県天理市の地主の主婦だった中山みきが開教したといわれています。
浄土宗の信者だった中山みきが、天保9年(1838年)長男の病気を治すために呼んだ山伏の加持代を務めたところ、親神(おやがみ)、天理王命(てんりおうのみこと)が憑依したとされています。その後、中山みきは親神のやしろとなって、その意志を伝えるようになったといいます。
その後中山家は没落したものの、中山みきは地元民の安産や病気治療をたすけ、信仰が広まったといわれています。
〖天理教の実際〗
親神、天理天命が世界を救済すると説き、平和で幸福な『陽気ぐらし』の実現を目指しています。本部は奈良県天理市にあり、人間創造の聖地『もとのぢば』と呼ばれています。『ぢば』は地場のことです。天理教の本部はおぢばと呼ばれています。
天理市の三島から川原城にかけては、信徒の宿泊所や教会関係施設の大学、図書館、病院が多く建ち並び、年間100万人を超える信徒が訪れる宗教都市になっています。
〖天理教の葬儀〗
世の中にはさまざま宗教、宗派があります。そのうちの一つが『天理教』です。奈良県に中心が置かれ、1800年代にまでその起源をさかのぼることができるといわれています。
今回は、この天理教の考え方、葬儀の特徴などについて解説いたします。
〖天理教の葬儀とは〗
天理教は江戸時代末の時代に中山みきを教祖として誕生した宗教団体です。奈良県天理市に本部があり、天理教の葬儀では魂の仮住まいとして神から借りていた古い身体を返し、新しい身体が見つかるまでの魂を神に預かってもらうための儀式とされます。
〖天理教の葬儀の特徴〗
天理教では、神様が人間に体を貸し与えているという考え方を持っています。神様は人間の親となり、その身を育み、さまざまなことを教えている、としているのです。このような考え方は、天理教の葬儀の内容にも現れています。
天理教においては亡くなることは『神様に体を返すこと』という解釈になります。神様に体を返した後に、また新しい体が見つかるまで、魂を神様にゆだねるという考え方をしているのです。これは『みたまうつし』と呼ばれる通夜にあたる儀式に象徴され、天理教の葬儀のもっとも大きな特徴です。
天理教は、神道の一種として考えられています。特に、昭和二十年まではこの傾向が顕著でした。
このため、天理教の葬儀は神道と似たかたちをとることになりますが、相談する相手は『神社』ではありません。全国各地にある教会が対象になります。
〖天理教の葬儀の流れ〗
〖通夜〗
1.祓詞を奏上する
お祓いの言葉を述べます。
2.みたまうつし
魂を体から移し、神の御許へと届けます。
3.供物を供える~礼拝
供物を神前に供えたり、斎主が玉串奉献を行ったりします。また、『しずめの詞』を唱えます。これは、みたまうつしを完了させるための詞であり、非常に重要なものです。
4.列拝と玉串奉献
世話役による列拝が行われたのち、参列者による玉串奉献が行われます。喪主(喪家)が玉串奉献をするのもこのタイミングです。
〖告別式〗
告別式でも供物をささげたり、告別式のための詞が奏上されたりします。また、玉串奉献も行うなど基本の流れは通夜と同様になります。
ただし、ここで挙げた流れは、あくまで一例にすぎません。同じ『天理教』でも、その葬儀のやり方には、ある程度の地域差などが存在します。
〖天理教での葬儀の香典マナー〗
香典には宗教ごとに表記などを適用したい部分があります。まず、天理教においては、蓮の花の書かれた香典袋は使いません。これは仏教の考え方によるものだからです。
表書きについては、神道に準じます。『御玉串料』『御榊料』『御霊前』などが一般的です。仏教ではよく使われる表書きである『御仏前』は、当然用いない方がよいでしょう。なお、この『御霊前』という表記は、天理教以外にもさまざまな宗教で用いられる表現でもあります。
水引きに関しては地域にもより、黄と白、あるいは黒と白、もしくは銀色のものを使います。これはどんな宗教でもいえますが、もちろん水引のかたちは結びきりです。
なお、香典返しの際には『偲草』という、ほかの宗教ではあまり使われない表記が用いられます。
天理教の玉串奉献のやり方について見ていきましょう。天理教の玉串のやり方は、神道のときと同じです。まず、両手で玉串を受け取ります。右手は手のひらを下に、左手は手のひらを上にして受け取るようにします。
この後、玉串を時計回り(右)に回して、祭壇側に茎を向けるかたちで静かに置きます。その後の参拝についてですが、これにも決まりがあります。
1.祭壇の前で2回礼をする(離れている場合は一礼とする場合もある)
2.柏手を4回うつ(ひかえめな音)
3.一拝する
4.柏手を4回うつ(ひかえめな音)
5.一礼をする
非常に特徴的なのは、この「柏手」の部分です。通常の葬儀においては、柏手は『忍び手』といい、音を立てることはしません。しかし天理教の場合は、必ずしも忍び手でなくてもよいとされています。これもまた、天理教の葬儀の大きな特徴といえるでしょう。
天理教の葬儀で不安なことがあれば、まずは相談から始めましょう。
ここまで、天理教の葬儀について見てきました。ただ、ここで挙げた内容はあくまで一般的なものです。実際の葬儀においては、これに加えて地域差や、それぞれの所属する教会により考え方の違いが生じる可能性がございます。