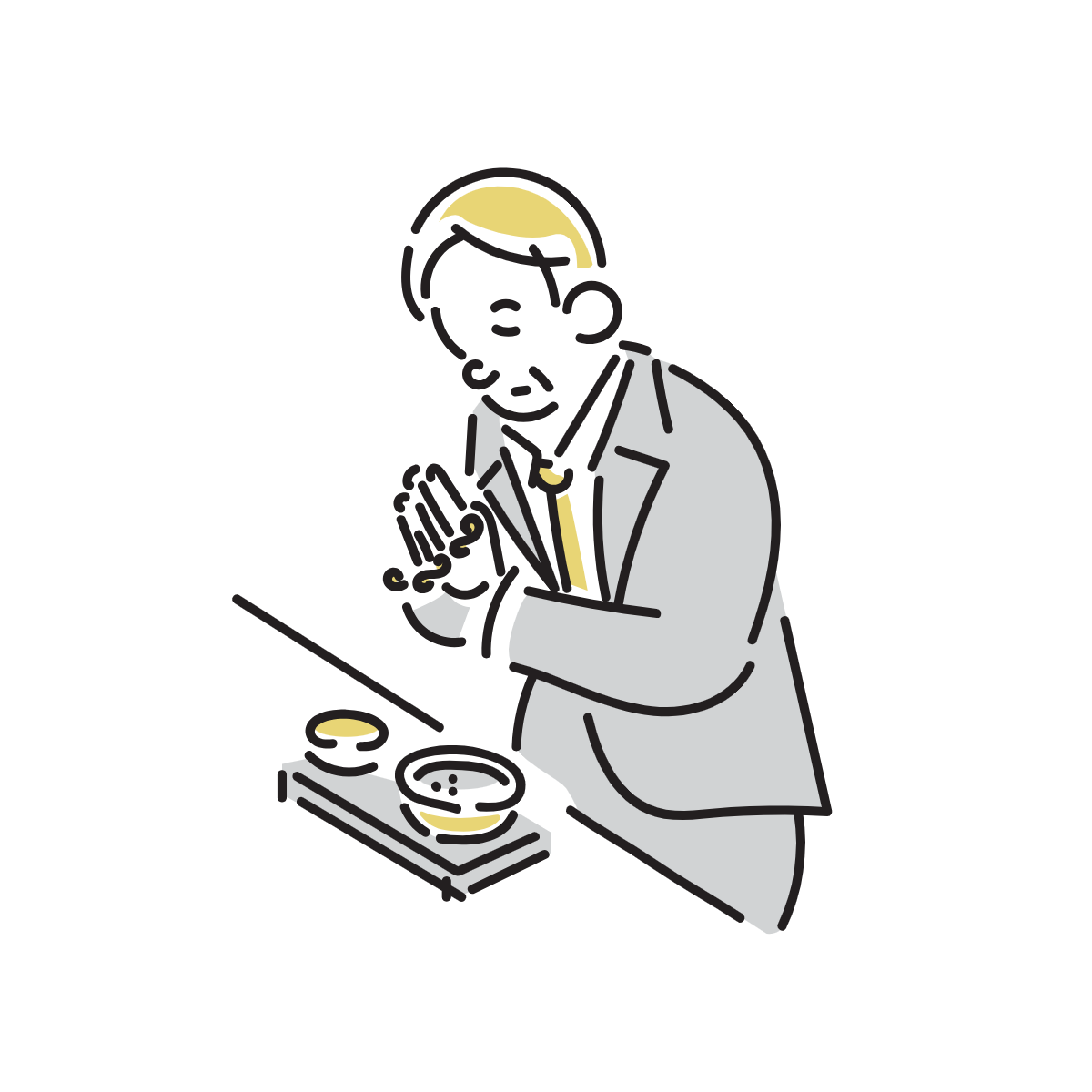【焼香とは】
焼香とは仏式の葬儀や、法事で抹香(まっこう)を焚く宗教的儀式のことです。
抹香は、樒(しきみ)の葉や皮を細かく砕いた木片です。
焼香ではこの抹香を手で摘み、香炉の中の焼香炭の上に落とし香りを出します。
仏壇に線香をあげることも焼香ですが、葬儀や法事は抹香を主に用いるため『焼香』という言葉自体が『抹香をあげること』を指します。
【焼香の意味】
焼香は、心身の穢れを落として故人に抹香の香りを捧げ、冥福を祈るためのものです。仏教において焼香の香りは仏の食物であるといわれており、故人や仏に食事を楽しんでもらい、来世での幸福を祈願するために焼香します。また、焼香をする私たちの邪気を祓い精神と肉体の穢れを取り除くともいわれています。
心と身体を清め、お参りをする作法ともいえます。
【焼香の作法】
宗派によって作法には多少の違いがありますが、大切なことは故人のご冥福を心を込めて祈る気持ちです。基本的な焼香方法は、まず右手の親指・人差し指・中指の3本(または、親指・人差し指)で抹香を少しつまんで、額の高さまでかかげます(押しいただく)。左の香炉の中心にある焼香炭の上に焼香を指でこすりながらパラパラと落とします。この際、数珠は左手にかけておきます。
抹香を香炉に落とし入れたら両手に数珠をかけ合掌。少し下がり遺族の方へ振り向き一礼して席に戻る。
【主な宗派の焼香の回数】
天台宗…特に決まりはない
真言宗…押しいただき3回
浄土宗…押しいただき1~2回
浄土真宗 本願寺派(西)…押しいただかず1回
浄土真宗 東本願寺派(東)…押しいただかず2回
臨済宗…1回(押しいただくかの定めなし)
曹洞宗…2回(1回目は押しいただき、2回目はそのまま落とす)
日蓮宗…押しいただき1回または3回
【様々な焼香の作法】
〇立礼(りつれい)焼香
立って行う焼香です。葬儀斎場・式場で行われており、遺影の前に焼香台が設置されています。順番が来たら席から立ち上がり、焼香台の前まで進み焼香を行います。夫婦で参列されている場合は、夫婦で一緒に焼香台の前まで進み、焼香は1人ずつ行います。
〇座礼(ざれい)焼香
和室(畳部屋)の式場や寺院,自宅での葬儀など椅子席が無い場合に、座ったまま焼香を行うことがあります。
基本的には立礼焼香と変わりありませんが、座礼焼香では焼香台まで進む際、腰を落とした低い姿勢のまま移動し、焼香は正座で行います。
〇回し焼香
自宅の葬儀など狭い会場で、焼香台までの導線確保が出来ない事があります。その場合焼香台は設置せずに、お盆に乗せた抹香と香炉を回して焼香を行う回し焼香という方法がとられます。
回し焼香は、焼香台に自分から行くことがないので焼香の所作が他とは少し異なります。
①番が回ってきたら、軽く礼をして香炉を受け取る。
②香炉を自分の前に置き、故人の遺影を仰ぎ一礼する。
③焼香を行う(主な宗派の焼香回数を参考に行ってください)
④両手に数珠をかけ合掌し故人の遺影を仰ぎ一礼。
⑤次の方へ香炉を回す。
【故人を想い丁寧なお焼香を行うことが大切】
宗派や作法がわからなくても、心を込めて故人や仏を想いお焼香するならば、やり方や作法にこだわることはないという考え方もあります。
また、個人の信仰の自由に基づき、自身の宗派の作法で弔うというのも一つの方法です。
焼香は心身の穢れを落とし故人に抹香の香り捧げ冥福を祈るためのものです。心を込めて故人をお見送りしましょう。