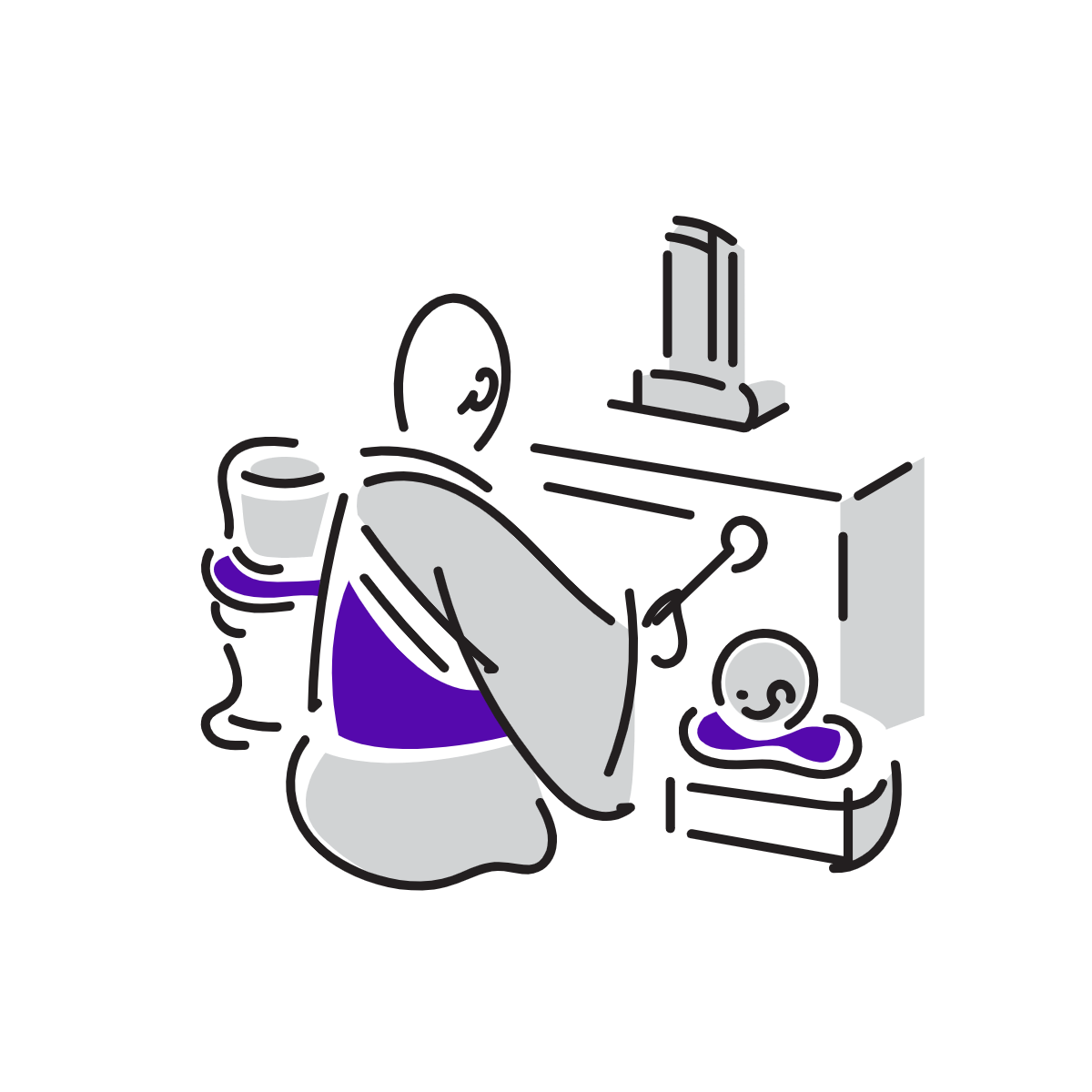【天台宗】
平安時代に最澄が開いた宗派で、本山は比叡山延暦寺です。
法華経を中心とする四宗(法華円教・戒・禅・密教)からなる大乗仏教全般を学ぶ宗派とも言われます。これは四宗相承とよばれています。天台宗の教えの一部をとりあげて、浄土宗,浄土真宗,臨済宗,曹洞宗,時宗,日蓮宗が生まれたともいわれています。
天台宗は法華経を中心にして大乗仏教全般を布教し、鎌倉仏教の多くの宗派を生み、後に山門派,寺門派,真盛派などと枝分かれして裾野を広げていきました。
天台宗は、中国の浙江省天台県にある天台山がそのルーツになります。最澄は天台山で修行し、日本に天台宗を伝えました。
天台宗の仏壇の本尊は釈迦如来ですが、阿弥陀如来,薬師如来,観世音菩薩,不動明王,毘沙門天など、菩提寺の本尊と同じものをまつります。
葬儀では、通夜や入棺の時に授戒式を行ったり、葬儀のあとに引導を行ったりする特徴があります。
今回は天台宗の考え方,葬儀の特徴,葬儀のやり方などについて解説していきます。
〖天台宗の葬儀〗
天台宗は『すべての人間はみんな、仏の子どもである』という視点を持っています。また、『真実を求め、追求する心があれば、それが悟りに繋がるのだ』という考え方を有している仏教でもあります。天台宗を象徴する言葉のうちの一つとして『一隅を照らす』というものがあります。これは『自分自身が輝くことで、周りの人も明るくすることができる。そうした人たちが手を結びあい生きていく世界は、仏の世界と同じである』といった考えであり、天台宗の根幹をなすものでもあります。
さて、この天台宗の葬儀においては❶顕教法要❷例時作法❸密教法要の3つが重要視されます。1つずつ見ていきましょう。
天台宗の掲げる経典は、法華経です。
❶の顕教法要では、この法華経を唱えることによって、日々の懺悔を行います。天台宗では、人はみな仏の子どもでありその身の内に仏性を宿しているので、懺悔することでこの仏性を高めるとしているのです。
❷の例時作法とは、お経を唱えることによって、死後に極楽に行くことを祈願するものです。また、お経を唱えることで、現世もまた極楽のようにすばらしい世界にするのだ、という願いも込められています。
❸の密教法要では、定められた印を作り、真言(仏のことば,真実のことば)で故人を弔います。これによって、故人は極楽に行くことができると考えられています。
〖葬儀の流れ〗
天台宗における、葬儀の流れを見ていきましょう。
通夜では、臨終の誦経(ずきょう)や通夜の誦経が行われます。これらはすべて亡くなったのちに行われるものであり、カトリックのお葬式のように旅立つ前に行われるものではありません。
『剃度式(ていどしき)』と呼ばれるものがあります。これは、水やお香を使って故人の身をお浄めする儀式のことです。『剃度』ということで、髪の毛にもかみそりをあてますが、現在では実際に剃髪をすることはほとんどありません。このときは「仏の元に出家する」という考えがとられます。
また、この剃度式が終わった後には戒名が与えられます。
ここまでが通夜で行われるものです。
葬儀の際は、導師によって『列讃(れっさん)』が行われます。穏やかな曲が流れ、打楽器が鳴らされます。阿弥陀如来に迎えられて故人が仏となり、その成仏をお祈りすることになります。
天台宗では、『お茶を供える』という儀式があります。列讃の後に棺が閉ざされるのですが、その際に茶器を供えるのです。これは『奠湯(てんとう)』『奠茶(てんちゃ)』と呼ばれる儀式です。
導師によって引導が渡されたのち、たいまつや線香などによって空中に梵字が描かれます。故人を称える文が唱えられ、弔辞などを読んだ後に読経を行うことになります。最後に回向文が唱えられて、葬儀は終わります。
〖焼香の作法、数珠の使い方〗
天台宗の焼香は基本3回とされています。合掌礼拝をした後、右手の3本の指(親指と人差し指と中指)を使って香をとります。その後、右手に左手を添えて額に押しいただき、焼香します。これを繰り返したのち、再度合掌礼拝を行います。
もっともこれは、あくまで一つの基準にすぎません。天台宗においては、焼香の回数も明確には決められていないので、1回でよいとするケースもあります。
線香を使う場合は、本数は1本か3本です。1本の場合は真ん中に立てますが、3本の場合はその後ろの左右にさらに2本を立てます。
特徴的なのは『数珠』です。天台宗では一般的な数珠とは異なり、丸い玉を連ねた数珠は使いません。天台宗に使われるのは、楕円形の平たい数珠です。一般的には、108個の『主玉』と4つの『天玉』そして1つの『親玉』が連なっており、親玉からさらに紐が伸びています。その紐には『弟子玉』が連なっています。
天台宗の数珠は、親指と人差し指の間にひっかけるようにして持ちます。そして、弟子玉が連なっている部分を下側に垂らして礼拝することになります。
【真言宗】
平安時代に弘法大師空海が開いた宗派で、本山は高野山金剛峯寺です。この身のままで仏になるという即身成仏を説いています。
修行は身口意の三密修行で、身体,言葉,心の修行を行うことで、誰でも仏になることができるとしています。
平安時代に貴族の間から広まり、加持祈祷を行いました。
真言宗は空海が中国の西安市にある青龍寺で恵果に学び、日本へ持ち帰った密教です。
分派が多いことでも知られる真言宗ですが、一般的に位牌や墓石の戒名に梵字の阿を刻みます。これは即身成仏をしたという意味です。
仏壇においては大日如来を本尊にまつります。
葬儀では授戒を葬儀式の途中に、引導に際しては灌頂を行うのが特徴です。
また、速疾成仏とも言われ、一刻も早く仏弟子にするということで、お経は小さい音で、早口で読まれるという特徴もあります。
実際の葬儀は、分派ごとや地方の習慣ごとに異なる進行で行われます。
〖真言宗の葬儀〗
真言宗は、平安時代に空海(弘法大師)によって開かれた仏教の一派です。真言宗では『密教』を基盤とする独特な葬儀が行われます。真言宗の葬儀には、以下の特徴があります。
・故人を大日如来の支配する『密厳浄土(みつごんじょうど)』に送り届けるための儀式
・今世で身についた悪い考えや習慣を落とすための儀式
・灌頂(かんじょう)と土砂加持(どしゃかじ)という特徴的な儀式がある
※灌頂(かんじょう)
故人の頭に水をそそぎかける儀式。仏の位にのぼることができるとされており、密教特有の儀式です。
※土砂加持(どしゃかじ)
洗い清めた土砂を火で焚き(護摩)、光明真言を本尊の前で唱えた後に、この土砂を遺体にかけて納棺するもの。この土砂は苦悩を取り除き、遺体にふりかけることで体が柔軟になるとされています。滅罪生善(めつざいしょうぜん)と呼ばれる行為です。
〖式次第〗
①僧侶の入場・法要前の密教の準備の行法
②塗香(ずこう),三密観(さんみつかん),護身法(ごしんぼう),加持香水(かじこうずい)の法
③三礼(さんらい):三礼文を唱えることで仏・法・僧への礼拝を行う
④表白(ひょうびゃく)・神分(じんぶん):大日如来をはじめとするさまざまな仏・菩薩に感謝を捧げ、加護を願い、故人の滅罪を願う
⑤声明(しょうみょう):仏典に節をつけた仏教音楽のこと
⑥授戒作法:仏僧に帰依することを宣言し、剃髪、授戒、授戒名により故人を帰依させる
⑦引導の儀式:再び表白・神分を行う。不動灌頂・弥勒三種の印明を授け、故人の即身成仏が果たされる
⑧墓前作法:破地獄の真言を与えて故人の心にある地獄を除き、金剛杵(法具)を授け、血脈(けちみゃく)の授与が行われる
⑨焼香~出棺:僧侶が諷誦文(ふじゅもん)を唱える間に焼香を行う。焼香後は僧侶が導師最極秘印という印を結び、3回指を鳴らしたあとに出棺する
〖焼香の作法〗
焼香の作法は宗派によって違いが見られる大きなポイントです。真言宗では、以下のように行われています。
①焼香台に進む
②焼香を3回行う。なお、香は額の高さまであげて押しいただく。
③合掌
参列者の数によっては、焼香を1回に短縮する指示が出ることもあります。
〖香典の包み方〗
真言宗では、葬儀の際の香典袋の表書きは、『御霊前』『御香典』といったものを使用します。入れる額は差出人の年齢・相手との関係性によってきますが、友人や会社関係者で5千円程度、身内になると1~10万円程度となります。
表書きの下にフルネームで差出人名を記載し、中袋には漢数字でいくら包んだのかを記載します。複数人で香典を用意する際は「〇〇一同」とし、中袋に個々の名前・金額・住所を記した明細を入れておきましょう。
香典袋は袱紗(ふくさ)に入れて持参するのがマナーです。
〖数珠の使い方〗
数珠も宗派によって違いが見られます。真言宗の数珠は振分数珠(ふりわけじゅず)と呼ばれるもの。108個が連なっている本連を使用します。
表裏に2本ずつの房がつき、親玉から数えて7個目・21個目に『四天』という小さな玉がついています。色は茶系統や黒、女性用では水晶を使用したものなどを選びましょう。両手の中指に数珠をかけ、そのまま手を合わせて使用します。房は自然に上から垂らしておきましょう。
なお、現代ではどの宗派でも使用できる略式の数珠もあるため、真言宗の信徒でない人が参列する際は、こうしたものを使用してもよいでしょう。
〖葬儀費用の相場〗
葬儀に必要な費用は、人数・場所を明確にした上で見積り金額を算出することができます。
仏式の葬儀費用として宗派ごとに違いが現れる点が、寺院に納める御布施になります。お付き合いの度合いや戒名の位によって金額に幅がありますので、目安を知りたい時は菩提寺のご住職にお伺いを立てましょう。
お布施とは別に、お車代・御膳料(会食に僧侶が参加されない場合など)に配慮してお気持ちを表現されるとよいでしょう。お車代・御膳料は5千~2万円程度が目安になります。
【浄土宗とは】
浄土宗とは法然を宗祖とし、阿弥陀仏を本尊とする仏教の宗派です。
極楽浄土に往生することができると説き、そのためには、阿弥陀如来の救いを信じ、南無阿弥陀仏を唱えます。念仏を唱えることで極楽浄土へ行くという考えは、他力と言います。
浄土宗では、浄土にいても、仏となってこの世に戻り、人々を救うことができるとしています。
本山は京都の知恩院(華頂山知恩教院大谷寺)です。
授戒、五重相伝を生前に受けると、位牌などの戒名が変わってきます。
浄土宗の戒名は鎮西派では誉号、西山派では空号がついているのが特徴です。また、戒名の最初に梵字が入ることもあります。
誉号は、五重相伝を終えた人に、院号は、寺院や社会貢献の度合いが高い人に与えられるものです。
居士、大姉、信士、信女などが位号になります。禅定門、禅定尼という位号もあります。
葬儀は、序分、正宗文、流通分に授戒と引導を合わせたものになります。仏を迎え、供養し、送るという3段階になっています。
焼香が、仏、法、僧の三宝へ三回行われるのも特徴の一つです。
浄土宗は鎌倉時代に法然上人により開かれました。本尊は阿弥陀如来です。総本山は知恩院(華頂山知恩教院大谷寺 京都市東山区)で、さらに全国に七大本山があります。
・増上寺(東京都港区)
・知恩寺(京都市左京区)
・清浄華院(京都市上京区)
・金戒光明寺(京都市左京区)
・善導寺(福岡県久留米市)
・光明寺(神奈川県鎌倉市)
・善光寺大本願(長野県長野市)
経典は『浄土三部経』が読まれ、『南無阿弥陀仏:なむあみだぶつ』と唱えます。浄土宗の教えは「阿弥陀仏の救いを信じて、『南無阿弥陀仏』と念仏を唱えれば必ず極楽浄土に往生できる」というものです。
念仏を唱えることで極楽浄土へ行くという考えは『他力』といいます。そして浄土にいても、仏となってこの世に戻り、人々を救うことができるとしています。
ちなみに日常的に使われる〈他力本願〉という言葉は、阿弥陀如来という絶対的な力を持つ他者の心を信じ頼る、というところから生まれた言葉だそうです。
〖浄土宗の葬儀〗
浄土宗の葬儀では、僧侶と共に故人に代わって参列者一同が念仏を唱える『念仏一会(いちえ)』があります。『南無阿弥陀仏』と念仏を10回から一定時間唱えることで、故人が阿弥陀如来の救いを得る助けをするという意味を持ちます。
さらに参列者と阿弥陀如来の縁を結ぶという意味もあるため、信者の信仰心を深めることが目的ではありません。
また僧侶による『下炬引導(あこいんどう)』という儀式が行われます。これは火葬時の点火を意味しています。僧侶が棺の前に進み焼香をしたあと、たいまつを意味する法具を2本取り、そのうち1本を捨てます。
これには『おんりえど(厭離穢土・煩悩にまみれたこの世を嫌い、離れること)』の意味があります。そして残りの1本のたいまつで円を描き、『下炬の偈(あこのげ)』を読み上げ終えたと同時にたいまつを捨てます。これは『ごんぐじょうど(欣求浄土・極楽浄土に往生したいと心から願い、求めること)』を表しています。
〖葬儀の流れ〗
通夜
故人を北枕に寝かせ、顔には白い布、胸元には守り刀を置きます。ろうそくと線香の火は、通夜の間絶やさぬよう気を配ります。
僧侶に枕経をあげていただきますが、本来は臨終の間際に安心して最期を迎えられるように行われたものですので、通夜では行わない場合もあります。
葬儀式
❶ 奉請(ぶじょう)
諸仏の入場を願います。
❷ 懺悔
❸ 剃度作法・十念
頭を剃る仕草をし十念を唱えます。
❹ 三帰三竟(さんきさんきょう)
仏・法・僧に帰依することを故人に伝える儀式です。
❺ 授与戒名
❻ 開経偈(かいきょうげ)
❼ 誦経(ずきょう)
❽ 発願文(ほつがんもん)
すべての衆生の救済につとめることを誓います。
❾ 摂益文(しゅうやくもん)
念仏を唱えるものは仏に守られるという偈のことです。
❿ 念仏一会(ねんぶついちえ)
感謝して念仏を数多く唱えます。
⓫ 回向(えこう)
念仏の功徳がすべての物の成仏に益することを願います。
⓬ 序分(じょぶん)
通常の法要に当たる部分で、序分、正宗分(しょうじゅうぶん)、流通分(るつうぶん)の三部構成で行われます。序分は葬場に諸仏を迎え入れ讃歎する儀式です。
⓭ 正宗分(しょうじゅうぶん)
引導を含む葬儀の中心部分となります。〖浄土宗の葬儀の特徴〗でお伝えした『下炬引導』はこの正宗分の儀式の中で行われます。
⓮ 流通分(るつうぶん)
法要を終えたことを感謝して諸仏と故人を送り出す儀式です。
浄土宗の葬儀における注意点・マナー
葬儀に参列する場合、宗派に合わせたマナーをあらかじめ知っておくことはとても大切なことです。
〖焼香の作法〗
浄土宗の焼香の回数には決まりはなく、寺院や地域によって違いがあるといわれていますが3回が基本です。
香炉の前に立ち合掌と一礼をし、親指・人差し指・中指の三指で香を軽くひとつまみしたら、その手を仰向けにします。香を持った手にもう片方の手を下から添え、額に押しいただき香炉の灰の中にくべます。最後に合掌と一礼をします。
〖香典の書き方〗
ご遺族(施主家)に渡す香典の表書きには、『御霊前』または『御香典』と書きます。
また、お寺に納める謝礼は『御布施』になります。『お経料』などの『〇〇料』とするのは商取引の支払いの意味合いをかもし出しますので、避けましょう。
浄土宗の葬儀の特徴や流れ、気をつけたい注意点などお話ししてきました。大切な方を送りだす儀式ですから、故人や遺族の納得のいく葬儀にしたいものですよね。
【浄土真宗】
浄土真宗本願寺派とは、浄土真宗の一派で、西本願寺を本山とします。
浄土真宗とは、浄土宗の開祖である法然の弟子、親鸞が始めた浄土教の一派です。
阿弥陀仏の力で万人が救済されるという絶対他力の教えで、信心があれば、往生するとすぐに成仏できるという考え方です。
そのため、授戒や引導などがありません。帰敬式といって、生前に仏弟子となった証しとして、おかみそりを行い、戒名ではなく法名をもらうことで帰依します。
浄土真宗の信者を門徒と呼びます。
浄土真宗は僧侶に肉食妻帯が許されています。明治期までは、妻帯が許されている唯一の仏教宗派でした。
浄土真宗は庶民を中心に広がった宗派で、明治の廃仏毀釈の影響をあまり受けずに今日に至っています。
浄土真宗は、本願寺派,大谷派,高田派など十派に分かれていて、国内では最も多くの寺院、信者がいるとも言われています。
浄土真宗本願寺派は、中でも一番規模が大きく、門徒数は700万人にもおよびます。
真宗大谷派の550万人と併せて浄土真宗の二大勢力となっています。また、浄土真宗全体では、18,880寺、1240万人以上もの人が信者であることから、日本で最大の規模を誇る仏教宗旨としても知られています。
〖浄土真宗の葬儀〗
これまでの葬儀や法要で我が家が浄土真宗だということまではわかっていても、いざとなるとその特徴や詳しい作法などがわからなくて不安だという方も多いと思います。今後喪主になる可能性がある方などはなおさらでしょう。
ここからは浄土真宗について知っておきたいことを解説していきます。
〖浄土真宗とは〗
浄土真宗の葬儀が他の宗派と大きく違う点は、『死者への供養として行われるのではない』というところです。なぜなら死と同時に阿弥陀如来によって極楽浄土に迎えられているため、成仏を祈る必要がないと考えられているからです。
ですから礼拝の対象は死者ではなく、阿弥陀如来になります。よって、浄土真宗の葬儀では、他の禅宗系の宗派にある「引導」や「授戒」がありません。
引導とは、葬儀の際に僧侶が棺の前で経文を唱える作法のことで、死者が悟りを得て成仏できるよう行うものです。
授戒とは、仏門に入るものに仏弟子としての戒を授けることをいいます。
〖浄土真宗の特徴〗
浄土真宗は、浄土宗の開祖である法然の弟子、親鸞聖人により創始されました。親鸞の死後いくつかに分派しますが、現在では浄土真宗本願寺派(本山:本願寺 通称:西本願寺)と真宗大谷派(本山:真宗本廟 通称:東本願寺)がほとんどの門派を抱えています。
本尊は阿弥陀如来で、経典は『浄土三部経』が読まれ『南無阿弥陀仏』と唱えます。お西・お東で唱える節が若干異なり、西:なんまんだーぶ(高音域の上り調子)と東:なんまんだぶ(低音域の下げ調子)が特徴的です。
浄土真宗の教えでは自力ではなく本尊である阿弥陀如来の本願力(他力)により、念仏を唱えれば『即身成仏』するとされています。
この『即身成仏』の教えから、死者の冥福を祈る必要がないのです。こういった考えから浄土真宗には他の宗派にはないさまざまな独自の作法があります。
また同じ浄土真宗の中にあっても、本願寺派と大谷派とでは葬儀の作法や荘厳(飾りつけ)、また日常のおつとめで読まれる『正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)』の節回しなど微妙な違いがあります。
〖浄土真宗の葬儀の流れ〗
〇本願寺派
臨終の際、末期の水は取らず故人は北枕に寝かせます。清拭,湯灌,エンバーミングなどの処置の後に白服をかけ(死後すぐに極楽浄土にたどり着いているので死装束は必要ありません)顔にも白布をかけます。通夜の後も「線香の煙を一晩絶やさない」などの習わしはありません。
納棺勤行(ごんぎょう)の後、葬儀が行われます。僧侶による読経,焼香と続き、ご遺族や参列者の焼香になります。
葬儀のあと出棺式が行われ、火葬・拾骨をします。その後は他の宗派同様、回向・法要に入る場合がほとんどです。故人は亡くなってすぐ仏様になっておられるので、故人のためではなく遺族の精進明けの儀式の意味合いがあります。僧侶に勤行をあげて短念仏を唱え儀式が終わります。
○大谷派
本願寺派同様、亡くなられたらすぐ極楽浄土に行って仏様になるという教えですので『冥福を祈る』『死出の旅路につく』という概念がありません。ですから守り刀を持たせたり故人に一膳飯をお供えすることなどは行いません。
大谷派の葬儀は『葬儀式第一』『葬儀式第二』と2段階に分かれているのが特徴的です。
まず葬儀式第一・棺前勤行を行い、次に葬場勤行で導師による読経、焼香が行われ遺族や参列者の焼香へと続きます。
その後に葬儀式第二を行います。昔は自宅葬が主流でしたが、現在では少なくなっており、仏間(葬儀式場)と火葬場での勤行も地域事情に歩み寄った形で、式次第が組み直されます。
以降、出棺式から回向・法要までは本願寺派と同様です。
〖浄土真宗の葬儀におけるマナー・作法〗
・焼香の作法
ご本尊の前で一礼し、お香を3本の指で摘むところまでは一般的なものと同じですが、本願寺派の場合お香を額に押しいただかずそのまま1回だけ香炉にくべます。大谷派は同様にして2回香炉にくべます。
香典袋の表書きの書き方
浄土真宗では、香典の表書きを『御霊前』ではなく『御仏前』と書きます。他の宗派では四十九日を過ぎて故人が仏様になると考えますが、浄土真宗では亡くなってすぐに仏様になるということで『御仏前』となるのです。本願寺派と大谷派ともに『御仏前』です。
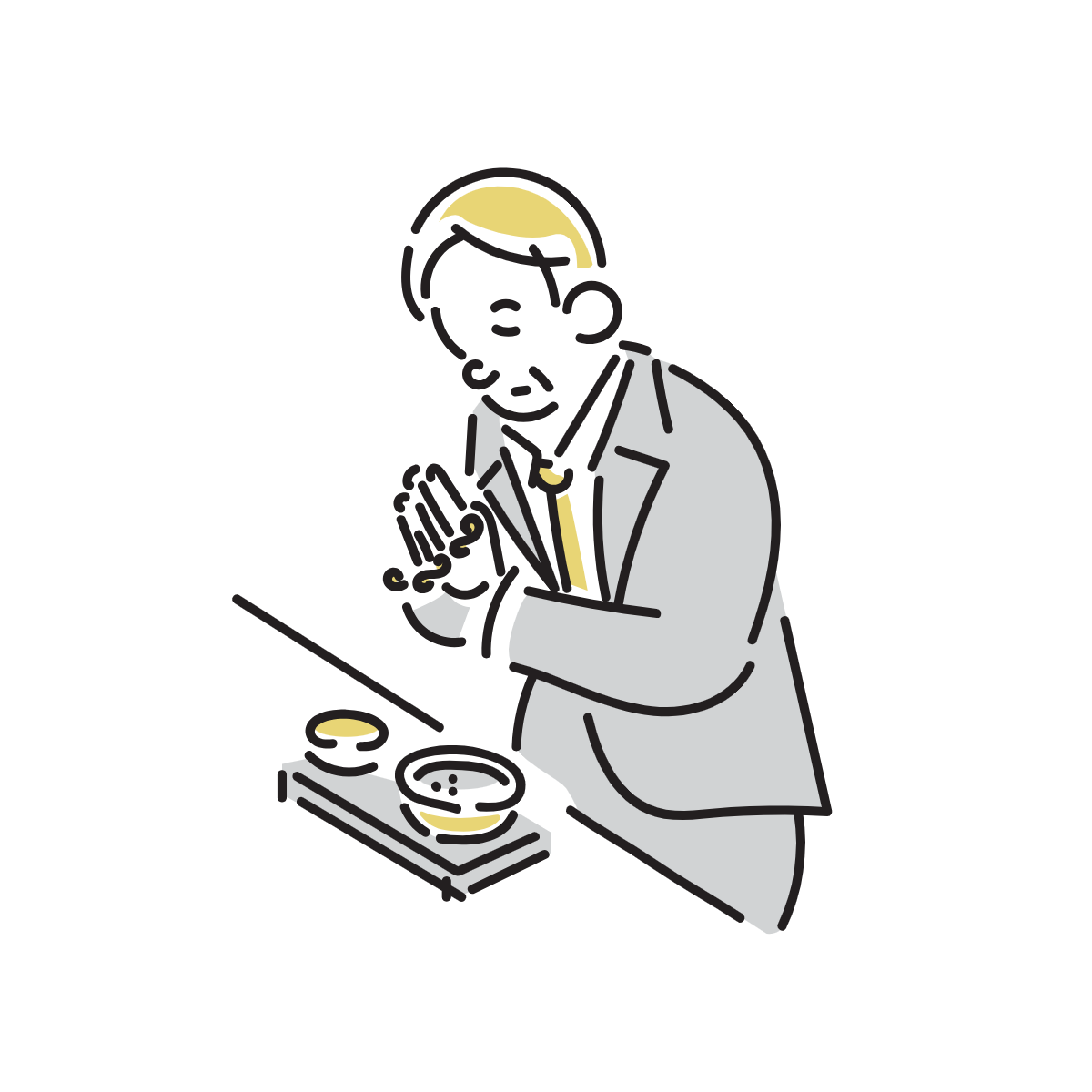
【臨済宗とは】
臨済宗は、禅宗のひとつです。
中国禅宗の五家七宗の一つが、鎌倉時代に明庵栄西が日本に伝えました。
看話禅は、師匠が出す公案という問題を、弟子が、体全体で答えを見出す中で、理論を超えた真実を探すというものです。また、師匠と二人きりで対面し、弟子が提示した結果を、師匠が検証する参禅を行うことで、体得しました。
浄土宗、浄土真宗の念仏を唱えて極楽浄土へ行く他力と比較して、坐禅によって悟りを得ることは、自力と呼んでいます。
厳しい武士の世の中の鎌倉時代では、武士を中心に坐禅が広がりました。
南無釈迦牟尼仏を唱えます。
臨済宗は、14とも言われる宗派があり、それぞれの菩提寺によって、葬儀などのマナーも変わります。
通夜、葬儀の白木位牌は、最上位に円寂の円の○が書かれます。
戒名には新帰元,戒名の下には霊位と書きます。
仏壇に位牌を祀る習慣は、臨済宗からスタートしたとも言われています。武家文化と深く結びつき、文化や政治に重んじられたのが臨済宗です。
臨済宗寺院のスタイルが、玄関,座敷などの生活習慣に大きな影響を与えたとも言われています。
【臨済宗の葬儀】
『仏教』と一括りにしても、そこにはさまざまな宗派があります。
特に、在来仏教と呼ばれているものは古くから成立していた伝統的な宗派で、日常生活の中でも非常によく目にする代表的な宗派です。
14の宗派がこの『在来仏教』に分類されており、葬儀式場や墓地では『在来仏教に限り葬儀・埋葬が可』としているところもあります。
今回はそのなかの一つである『臨済宗』について取り上げ、その宗派の考え方と葬儀のあり方、流れについて解説していきます。
〖臨済宗の葬儀とは〗
臨済宗は日本仏教において禅宗(臨済宗・曹洞宗・日本達磨宗・黄檗宗・普化宗)の1つです。鎌倉時代以降、日本にも広く普及しました。臨済宗の葬儀では故人を仏の弟子にするため授戒という儀式と、仏の世界へと導くために引導の儀式が中心に行われます。
〖臨済宗の葬儀の特徴〗
臨済宗は『禅宗』の一つに分類されており、
鎌倉時代に伝わったといわれています。
『禅問答』という言葉もありますが、自分自身と語り合い、自分自身を見つめることで悟りを開いていくという考え方があります。
葬儀は大きく分けて、授戒(仏門に入るために戒律を授けること)・念誦(ねんじゅ。詳しくは後述しますが、経典などを口にすること)・引導(導師が亡くなった方を仏門に導き入れること。浄土に旅立たせること)によって構成されています。
特に引導においては、『法語(言葉によって、仏教の正しいあり方や教えを伝えること)』が用いられます。
『臨済宗の葬儀の流れ』
葬儀の流れは、以下の通りです。これはあくまで『基本』であるため、ほかの宗教・宗派の葬儀と同様、地域差が見られることがあります。
➊葬儀の意義
まず、導師(臨済宗における宗教者の呼び方)が入場します。その後で剃髪(ていはつ)を行います。これは髪の毛を剃る儀式ですが、現在は『カミソリをあて、剃る素振りに留められて』います。
この後に行われるのが『懺悔文(ざんげもん)』と呼ばれる行程です。亡くなる前後に、今までの人生の行いを悔いたり、罪の許しを乞うたりすることは世界各国の宗教で見られることですが、臨済宗でも同じように行います。
そのあとで、仏の教えに帰依することを誓う『三帰戒文(さんきかいもん)』浄めの儀式である『三聚浄戒(さんじゅうじょうかい)』『十重禁戒(じゅうじゅうきんかい)』が行われます。これによって、仏門に正式に入ることになります。その後、香をたきます。
❷入棺~説法
故人が棺に入り、また閉じられるときには、特別な念誦が唱えられます。念誦とは心のなかで、あるいは口に出して仏や経文を唱えることを指す言葉であり、これは出棺のときにも行われます。
特徴的なのは『山頭念誦』と呼ばれる儀式です。これは、故人の成仏を願って『往生咒(おうじょうしゅ)』を唱え太鼓を打ち鳴らす儀式をいい『鼓ばつ』と呼ばれることもあります。また、その後に導師によって引導の法語が唱えられることになります。
〖臨済宗の焼香の作法〗
『焼香』は、仏教の葬儀に参加する際に必ずといってよいほど行うものです。ただそのやり方は、宗派によって多少の違いがあります。臨済宗のやり方について見ていきましょう。
1.仏前で合掌し、礼拝する
2.抹香をつまみ、香炉に入れる
3.合掌して礼拝する
これが一連の流れです。
臨済宗において、焼香は1回だけにするのが基本です。また、宗派によっては、一度抹香を額にいただいてから焼香することもありますが、臨済宗ではこのような行動はいたしません。もっとも、これも多少の違いが見られます。なかには2回もしくは3回の焼香を行うケースもあります。
また、額にいただくことも禁じられている訳ではありません。ちなみに、より丁寧に2回行うときは、それぞれ『主香(1回目)』『添え香(2回目)』と、別々の呼び方をされるケースもあります。このように焼香の回数も、額にいただくかどうかも、明確な『決まり』があるわけではないのです。『1回のみでもよい、額にはいただかなくてもよい』というのを基本として覚えておきましょう。
〖まとめ〗
臨済宗では、『自分と向かい合うこと』を考え方の基本としています。その葬儀は、授戒・念誦・引導の3つによって構成されています。地域にもよりますが、太鼓を打ち鳴らして行われる葬儀は、臨済宗の大きな特徴だといえるでしょう。また、焼香のやり方についても特徴があります。
このように臨済宗の葬儀は、ほかの在来仏教とは異なる部分も多く、なかなか複雑な面もあります。また、臨済宗の僧侶になるための修業は、仏教の中でも特に厳しいと言われており、厳格なご住職が多い傾向にあるようです。
【曹洞宗とは】
曹洞宗は、禅宗の一つです。鎌倉時代に道元が中国から日本へ伝えました。
本山は、福井県の永平寺と横浜市の總持寺です。
坐禅を修行の中心に据え、只管打坐というただひたすらに坐禅を行うことを、最も重視します。
即心是仏という、坐禅の状態で日常生活を生きていくことを説きます。
禅戒一如とも言い、坐禅で学んだことが、生活に現れるという考えからです。
南無釈迦牟尼仏を唱え、釈迦を本尊とします。
臨済宗の看話禅が対話型の禅であることに比較して、曹洞宗の黙照禅は、黙々と座ることによって、人が持つ仏の心性があらわれ、仏徳がそなわるとしています。
曹洞宗の仏壇では、一仏両祖の三尊仏形式で祀ります。本尊は釈迦牟尼仏で、右に高祖承陽大師道元禅師、左に太祖常済大師瑩山禅師を飾るか、一仏両祖を一本とした、三尊仏の掛け軸を飾ることもあります。
禅宗の葬儀は、今の仏式葬儀の元になったとも言われています。曹洞宗の葬儀では、授戒と引導が中心になります。
仏前に唱えるお経は、修証義や般若心経が中心です。
また、宗派の日本分布図という観点で見ると、曹洞宗は他の方面に比べて東北方面で多く普及している(檀信徒が多い)と言われています。
これはかつて大本山の永平寺、總持寺に次ぐ第三本山ともいわれた東北地方初の曹洞宗寺院である正法寺(創建は貞和4年(1348年))の建立によるもの。
日常生活を修行とみなす『禅』の考え方が日々規則正しい生活をくりかえしていた農民にはわかりやすく、浸透していったため。
といくつかの諸説があります。
〖曹洞宗の葬儀〗
同じ仏式の葬儀といえども、宗派によってマナーや流れに特徴があることがあります。曹洞宗はそうした宗派のひとつです。曹洞宗での葬儀には、ほかの宗派での葬儀では見られない特徴があります。
今回は、曹洞宗の葬儀で見られる特徴や独自の流れなどをご紹介します。
【曹洞宗の葬儀】
〖曹洞宗の葬儀とは〗
曹洞宗は、仏教の中でも禅宗と呼ばれる宗派の一派です。曹洞宗の葬儀には、独自の役割が考えられています。
・死後にお釈迦様(釈迦如来)の弟子になるために行う
・弟子になるために必要な戒名・戒法を授かるための『授戒(じゅかい)』を行う
・悟りを開くために、仏の道へ導くための『引導』を行う
この『授戒』と『引導』が曹洞宗の葬儀のポイントになります。
〖曹洞宗葬儀の式次第〗
曹洞宗の葬儀の流れは、他の宗派に比べて特徴的です。
剃髪(ていはつ)の儀式:導師(引導を渡す僧侶)が剃髪を行う
↓
授戒:後に説明する5種類の儀式を行う
↓
入棺諷経(にゅうかんふぎん):読経、焼香を行う
↓
龕前念誦(がんぜんねんじゅ)
↓
挙龕念誦(こがんねんじゅ):曹洞宗葬儀での特徴のひとつ、太鼓やハツを鳴らす鼓鈸三通(くはつさんつう)を行う
↓
引導法語:導師が故人の生前を漢詩で表し、松明で円を描き、悟りの世界に導く
↓
山頭念誦(さんとうねんじゅ)
↓
出棺:再度、鼓鈸三通を行い、出棺する
《授戒で行う儀式》
・酒水(しゃすい):清い水を手向ける
・懺悔文(さんげもん):生涯で犯した罪を反省する
・三帰戒文(さんきかいもん):仏陀の教えを守り修行者として帰依することを誓う
・三聚浄戒(さんじゅうじょうかい)・十重禁戒(じゅうじゅうきんかい):導師が用意した法性水を故人の頭や位牌に注ぐ
・血脈授与(けちみゃくじゅよ):血脈を霊前に供える。血脈とはお釈迦様から故人へと続く仏法の系譜を記したもののこと
〖曹洞宗葬儀の焼香の作法〗
焼香の方法は宗派によって異なるポイントのひとつです。葬儀に行くたびに迷われる方も多いことでしょう。曹洞宗では、以下のように焼香を行います。
焼香台に進む
↓
焼香台の2,3歩程度手前で立ち止まり、ご本尊,遺影,位牌に軽く一礼
↓
焼香台まで進み、右手でお香をつまむ
↓
軽く左手を添えて額に押しいただき、念じてから焼香をする(正念)
↓
1度目に焼香したお香のそばに2度目の焼香をする(従香(じゅうこう))2度目は額に押しいただかない
↓
数珠を両手にかけ、合唱・礼拝
ポイントは、『焼香は2度』『1度目は額に手を持っていき、2度目はそのまま』という2点です。なお、会葬者が多い際には『焼香は1回で』と指示されることもあります。
〖曹洞宗葬儀の香典の包み方〗
葬儀に参列する際に迷いがちなものが香典の表書きです。曹洞宗では、『御霊前』または『御香典』を使用します。
筆ペンを使用し、水引の下中央に差出人名をフルネームで記載します。複数人で香典を渡す場合は、『〇〇一同』などとするケースもあります。その際は中に個々の名前と金額・住所を記載した明細を同封しておきましょう。
金額は一般的なものと変わりません。友人であれば5千~1万円程度、勤務先の関係者であれば5千円程度、身内の場合は年齢・間柄によって変動しますが、1~10万円の間となります。
お札は、香典の場合、新札は不適切だとされることが多いです。そのため、綺麗なお札の場合は一度折るなどしておきましょう。かといって、汚れていたりあまりにもくしゃくしゃになっていたりするお札を使うことも不適切です。
お札を入れた中袋は、左・右の順に上包みの紙をかぶせ、上側が下側にかぶさるように包みます。
〖曹洞宗葬儀の費用相場〗
曹洞宗の葬儀本体に必要な葬儀費用は、人数・場所を明確にした上で見積り、金額を算出することができます。
仏式の葬儀費用として宗派ごとに違いが現れる点が、寺院に納める御布施になります。お付合いの度合いや戒名の位により金額に幅がありますので、目安を知りたい時は菩提寺のご住職にお伺いを立てましょう。
御布施とは別に、お車代・御膳料(会食に僧侶が参加されない場合など)に配慮してお気持ちを表現されるとよいでしょう。お車代・お膳料は5千~2万円程度が目安になります。
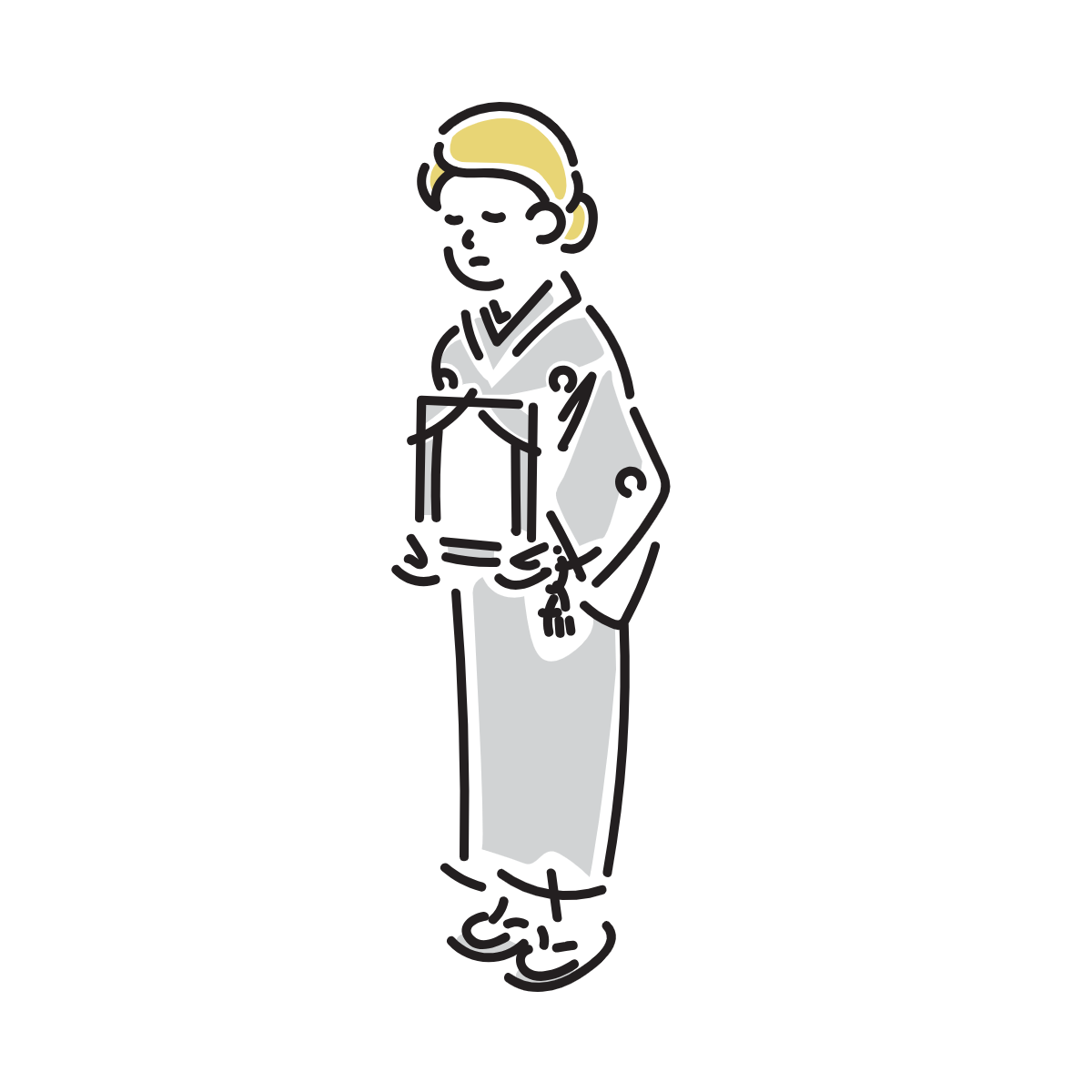
【日蓮宗とは】
日蓮宗とは、鎌倉時代に日蓮によって始まった仏教の一派です。
妙法蓮華経を唱えるので、日蓮法華宗とも言われています。
日本人の宗祖の名前が宗派名になっているのは、日蓮の日蓮宗のみです。
南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)の七文字は、本仏の声そのものという考え方です。
日蓮入滅の日のお祭りは、お会式(おえしき)と呼ばれています。池上本門寺(東京)の10月12日のお会式での万灯行列が有名です。
日蓮宗の仏壇では、中央の本尊には、日蓮聖人や、三宝尊のいずれかを祀ることが多く、右に鬼子母神、左に釈迦牟尼仏や大黒天を祀ります。
また、日蓮が写した御曼荼羅を本尊とするという寺院もあります。鎌倉比企ヶ谷・妙本寺に奉安されている『臨滅度時のご本尊』を推薦する寺院もあるので、仏具店でそろえるよりは、菩提寺の住職が書き写したものを祀るのが正式とも言われています。
葬儀では、引導がありません。また、戒名と言わずに法号と言います。三角巾や六文銭の死装束も用いない考え方もあります。
【日蓮宗の葬儀】
故人が生前に信仰していた宗教がある場合、葬儀はその宗派の作法に沿って行うことになります。たとえば、故人が日蓮宗を信仰していたのであれば、日蓮宗における葬儀の作法に則って進める必要があり、葬儀社を選ぶときも日蓮宗の進め方を熟知しているところにお願いしなければならないでしょう。ここでは、日蓮宗の葬儀の特徴や葬儀の流れ、葬儀の費用などについて解説します。
〖日蓮宗の葬儀とは〗
日蓮宗は日蓮聖人が開祖の宗教で、南無妙法蓮華経の題目を唱えることが、何よりも重要な修行となっています。それゆえに日蓮宗の葬儀の際には頻繁に南無妙法蓮華経を唱えます。
〖日蓮宗の葬儀の特徴〗
日蓮宗の開祖といえば日蓮聖人です。日蓮聖人の教えでは、日蓮宗の中心的な経典である法華経の功徳を信者が施し信仰を深めるためには、法華経の功徳が込められているとされる『南無妙法蓮華経』の七文字のお題目を唱える修行が重要だとされています。
『南無妙法蓮華経』のお題目を繰り返し唱えることによって法華経への信心の深さを示すことができ、死後には『霊山浄土(りょうぜんじょうど)で釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)にお会いし、成仏することができる』というのが、日蓮宗の教えです。
葬儀においても『南無妙法蓮華経』というお題目を唱えることが重要で、葬儀の最中にもこのお題目が唱えられます。葬儀の場でお題目を唱えることによって『故人の生前の信心深さを讃え、故人が無事に霊山浄土に辿り着き成仏する』手助けができるため、功徳を積むことになり修行が進むとされています。
〖日蓮宗の葬儀の流れ〗
故人が亡くなった日の夜、または次の日の夜などに通夜を行い、その翌日に葬儀・告別式を実施するのが一般的なお葬式の流れになります。葬儀・告別式は、遺族の集合,受付準備を含めて午前10時頃に開始され、約2時間で閉会するのが通例です。
一般的に、司会者(葬儀社)による開式の宣言がなされ、僧侶による読経が開始されます。その際、日蓮宗の場合『総礼』⇨『道場偈』⇨『勧請』⇨『開経偈』と続き、参列者全員で『読経』⇨『唱題(お題目を唱えること)』で経本を読み上げ、『南無妙法蓮華経』を唱えるようになります(地域により多少異なります)。
その途中に、日蓮宗独自の『開棺』『引導』と呼ばれる儀式が行われます。『開棺』とは、僧侶が棺の傍に立って棺の蓋を叩き、音を立てながらお経を読み、お供物のお花やお茶、お膳などを祭壇に捧げる儀式です。
『引導』は仏様に故人を引き合わせる儀式で、僧侶は払子(ほっす)と呼ばれる麻や獣毛などを柄につけた仏具を振り、引導文を読みます(宗教者により作法が異なる場合があります)。
〖日蓮宗の焼香のマナー〗
葬儀の際の僧侶による読経が終了すると、その後に『南無妙法蓮華経』を唱える唱題が行われ、その間に参列者は焼香を行うことになります。日蓮宗の場合、合掌し一礼して焼香盆の中のお香を右手の親指・人差し指でひとつまみ取って火種に振りかけます。
焼香は3回行うのが日蓮宗の導師の正式な作法とされています。一般参列者の場合は概ね1~3回です。数珠を左手に持ち右手でお香を火種にくべた後、再び合掌一礼し席へ戻ります。線香を立てる形式の焼香では1本または3本立てます。
〖日蓮宗の香典のマナー〗
『香典』とは、本来は『亡くなった方の霊前にお供えする、線香や花の代わりになるもの』のことです。ただ、香典には、突然のご不幸に対する相互扶助的な意味合いや気持ちが込められており、現代では『亡くなられた方へお供えする金品』になっています。
日蓮宗の香典では、葬儀のときから四十九日の手前の法要までについては、不祝儀袋の表書きには『御霊前』または『御香典』と書きます。そして、葬儀終了から四十九日以降の法要時には『御仏前』『御香典』と書くようにしましょう。日蓮宗では、亡くなられた方は四十九日を境に成仏されるという考え方をするため、このような区別があります。
【まとめ】
この他にも沢山の宗派があり
伝統的には〖13宗56派〗と数えられています。
その多くの日本人が葬儀で仏式を用いています。