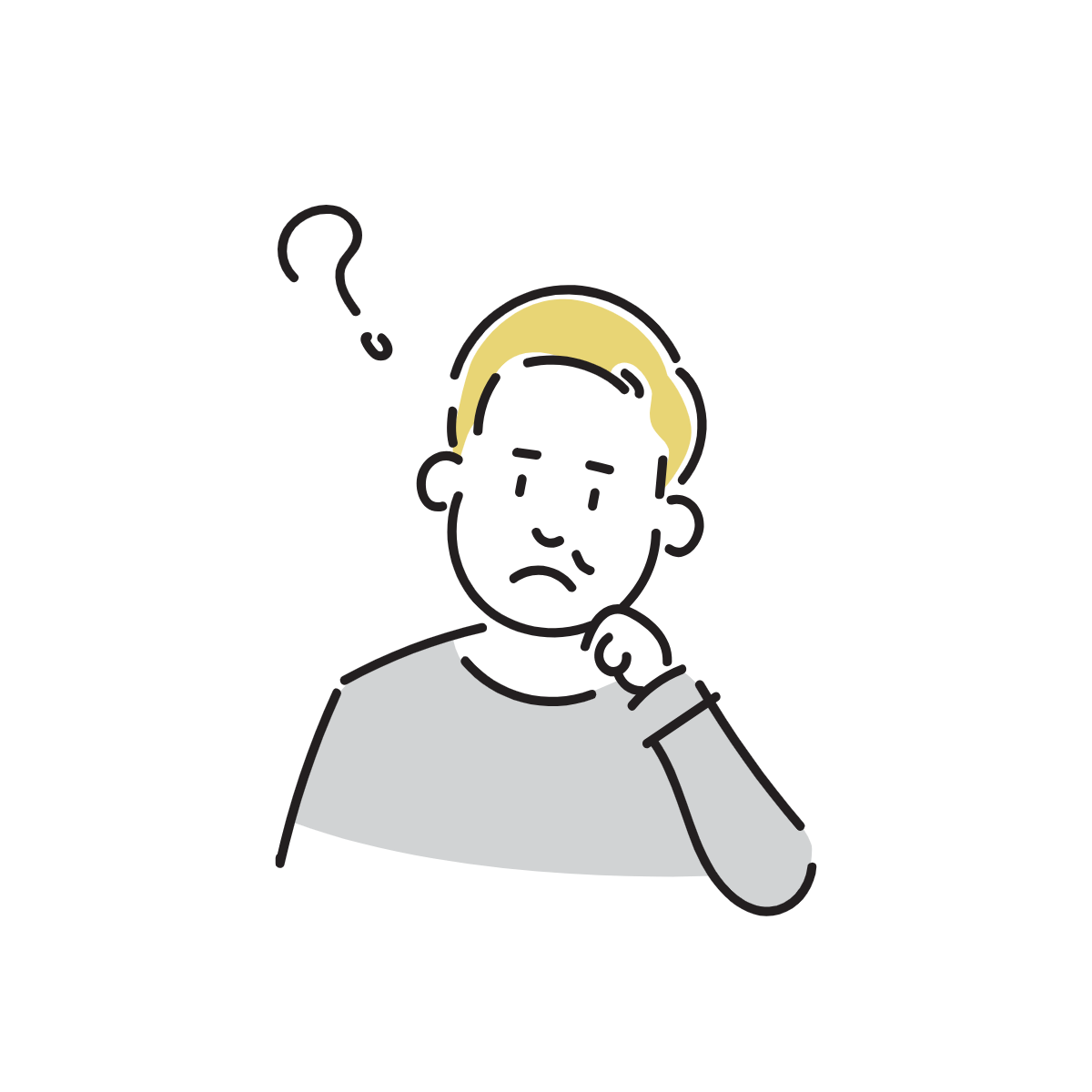葬儀に関する用語は、日常生活では使うことのない特殊な言葉であることがほとんどです。
そのため、『漢字が読めない』『いつ使う言葉か分からない』などといったこともあるでしょう。
そこで今回は、お通夜,告別式(葬儀),火葬,法要で使われる用語について解説します。
はじめに葬儀や法要でよく使われる、基本的な用語を確認してみましょう!
・焼香(しょうこう)
・線香(せんこう)
・読経(どきょう)
・お布施(おふせ)
・袱紗(ふくさ)
・忌み言葉(いみことば)
・喪主(もしゅ)
・香典(こうでん)
・香典返し(こうでんがえし)
・弔問(ちょうもん)
〖焼香(しょうこう)〗
『焼香』とは、お通夜や葬儀の際に、細かく砕いたお香(抹香)をひとつまみ掴み、香炉に落として焚きます(押しいただいてから香炉に落とす場合もある)。
回数や作法は、宗派によって異なります。
〖線香(せんこう)〗
『線香』は、焼香よりも馴染みが深く、線香に火を付けて香炉に立てて手を合わせることです(立てずに寝かせる場合もある)。
焼香同様に本数や作法は、宗派によって異なります。
〖読経(どきょう)〗
『読経』とは、お通夜,葬儀,法要で僧侶がお経を読み上げることです。
〖お布施(おふせ)〗
『お布施』とは、お通夜・葬儀・法要で供養していただいた僧侶へのお礼として渡すお金のことです。
〖袱紗(ふくさ)〗
『袱紗』とは、結婚式などでも使われる金封を包む布のことです。
〖忌み言葉(いみことば)〗
『忌み言葉』とは、葬儀や結婚式などの儀式においてふさわしくない言葉のことです。
葬儀においては、不幸が重なると捉えられるため『再三』『次々』『益々』といった重ね言葉はタブーとされています。
〖喪主(もしゅ)〗
『喪主』とは、葬儀を執り行う中心の人物のことです。
一般的に、故人との関わりが一番近い人が喪主を務めます。
〖香典(こうでん)〗
現代の『香典』とは、御霊前にお供えするお金のことです。
むかしは、食料などを提供して葬儀の会食にかかる負担などを助け合っていたと言われています。
〖香典返し(こうでんがえし)〗
参列者からいただいたお金に対し、葬儀後にお礼として喪主・遺族からお品物を送ることを『香典返し』と言います。
受け取った香典の3分の1または、半分の額が香典返しの相場です。
〖弔問(ちょうもん)〗
『弔問』とは、故人の自宅または遺族の自宅を訪ねて、お悔やみを述べることです。
葬儀に参列できなかった方のなかには、線香をあげる方もいますが、これも弔問と呼びます。
続いて、故人が亡くなった直後からお通夜・葬儀までに使う用語を確認してみましょう!
・末期の水(まつごのみず)・死に水(しにみず)
・枕直し(まくらなおし)
・枕飾り(まくらかざり)
・枕経(まくらぎょう)
・枕飯(まくらめし)
・湯灌(ゆかん)
・旅支度(たびじたく)
・仏衣(ぶつい・ぶつえ)・死装束(しにしょうぞく)
・納棺(のうかん)
〖末期の水(まつごのみず)・死に水(しにみず)〗
死亡が確認された後に、故人の口元へ水を運ぶ儀式を「末期の水」または「死に水」といいます。
『安らかに眠ってほしい』というような説のあるものです。
医師や病院の方から促されるかたちで行われるでしょう。
〖枕直し(まくらなおし)〗
『枕直し』とは、ご遺体を安置する際に頭を北・足元を南に向けて寝かせることです。
〖枕飾り(まくらかざり)〗
『枕飾り』とは、逝去してからお通夜や葬儀までの期間、安置する場所の枕元に用意する簡易的な祭壇のことです。
宗派や地域によって、内容は異なります。
〖枕経(まくらぎょう)〗
『枕経』とは、ご遺体を安置している場所の枕元でお経をあげることです。
枕元には枕飾りが置いてあります。
〖枕飯(まくらめし)〗
『枕飯』とは、故人が生前に使っていたお茶碗に炊いたお米を入れ、お箸をさしたものです。
故人最後の食事とされており、自宅で安置する場合は、葬儀・火葬日まで毎日お供えします。
〖湯灌(ゆかん)〗
『湯灌』はご遺体をぬるま湯で、拭いて清めることです。
遺族が行う場合や、専門業者のスタッフが行う場合などさまざま。
湯灌が終わり、着付け、納棺といった流れで行われます。
〖旅支度(たびじたく)〗
『旅支度』とは、棺に収める前の準備です。
ご遺体を清めた後に、仏衣や足袋を着用させるなど棺に収める前に必要な支度を行います。
〖仏衣(ぶつい・ぶつえ)・死装束(しにしょうぞく)〗
『仏衣』『死装束』とは、ご遺体に着せる白い着物のこと。
〖納棺(のうかん)〗
『納棺』はご遺体を清め、旅立つ準備を終えて棺に収めることをいいます。
続いて、お通夜で使う用語です。
参列者が訪れるお通夜の前に、遺族との時間を設けるための儀式が『仮通夜』
本来の意味は『近親者で故人の体を見守る』というものでしたが、近年では執り行われないことも多いです。
・通夜振る舞い(つやぶるまい)
『通夜振る舞い』とは、お通夜の後に参列者や僧侶に向けた会食のことです。
大皿を分けて食べるスタイルが一般的でしょう。
次に、告別式・葬儀で使う用語を確認していきましょう。
・戒名(かいみょう)
・位牌(いはい)
・塔婆(とうば)
・弔辞(ちょうじ)
・弔事(ちょうじ)
・弔電(ちょうでん)
・供物(くもつ)・供花(きょうか・くげ)
・会葬礼状(かいそうれいじょう)
・御仏前(ごぶつぜん)・御霊前(ごれいぜん)
・精進落とし(しょうじんおとし)
〖戒名(かいみょう)〗
『戒名』とは、仏の世界へと入ったことを意味する名前のことです。
本来は出家などにより、生前に受けるものでしたが今では『極楽浄土に行けるように』といった願いから故人に戒名を授けています。
〖位牌(いはい)〗
『位牌』とは、故人の戒名や命日が記されたものです。
故人の霊魂が宿る場所とも言われています。
〖塔婆(とうば)〗
『塔婆』とは、墓石の横からのぞく細長い木製の板のことで、仏の世界を表す文字が書かれています。
また、故人への手紙の役割を果たすため、供養のシンボルとも言われています。
〖弔辞(ちょうじ)〗
『弔辞』とは、告別式や葬儀で故人と生前親しい仲だった友人や知人が、別れを惜しむ言葉を述べることをさします。
喪主や遺族が、故人の遺志などから弔辞を依頼します。
〖弔事(ちょうじ)〗
『弔事』とは、葬儀などのお悔やみごとのことです。
反対を表す言葉は、結婚式などのお祝いごと『慶事』
〖弔電(ちょうでん)〗
『弔電』とは、葬儀に参列できない方がお悔やみの気持ちを伝える電報のことです。
反対を表す言葉は、結婚式などに送る『祝電』
〖供物(くもつ)・供花(きょうか・くげ)〗
『供物』とは、葬儀の際に故人や遺族へお悔やみの気持ちを表すために送るお供え物です。
果物・お香・ろうそく・花などが一般的で、供えるお花のことを『供花』といいます。
〖会葬礼状(かいそうれいじょう)〗
会葬とは、葬儀に参列することです。
そのため『会葬礼状』とは、会葬・香典・弔電・供花などのお礼状をさします。
〖御仏前(ごぶつぜん)・御霊前(ごれいぜん)〗
『御仏前』とは、文字通り仏の前のことで、成仏して仏になった故人に向けた言葉です。
『御霊前』とは、成仏する前の故人に向けているため、一般的に四十九日前に使います。
〖精進落とし(しょうじんおとし)〗
『精進落とし』とは、葬儀や火葬後・火葬中の会食のことをさします。
従来は、四十九日の忌明けに精進落としを食べていました。
続いて、火葬で使う用語を確認しましょう!
・別れ花(わかればな)
・出棺(しゅっかん)
・骨上げ(こつあげ)・拾骨(しゅうこつ)
・納骨(のうこつ)
・分骨(ぶんこつ)
〖別れ花(わかればな)〗
『別れ花』とは、棺のなかに入れる花のことです。
一般的に供花を使うことが多いですが、故人が生前に好きだった花を用意して入れることもあります。
〖出棺(しゅっかん)〗
『出棺』とは、ご遺体を葬儀場から火葬場まで移動させることです。
遺族や近い親族など、火葬場に行かない方にとっては故人との最後のお別れです。
〖骨上げ(こつあげ)・拾骨(しゅうこつ)〗
『骨上げ』『拾骨』とは、火葬後の遺骨を二人一組で骨を拾い上げることです。
『収骨』も同じ読み方・意味を持ちます。
〖納骨(のうこつ)〗
『納骨』とは、火葬され骨壷に拾骨した後、お墓などに安置することです。
〖分骨(ぶんこつ)〗
『分骨』とは、遺骨を2箇所以上の場所に納骨することを言います。
お通夜や葬儀、火葬以外の法要で使う用語を集めてみました。
・霊供膳(りょうくぜん・れいくぜん)
・年忌法要(ねんきほうよう)
・改葬(かいそう)
・忌中(きちゅう)・喪中(もちゅう)
・忌明(きあけ)
・初七日(しょなぬか・しょなのか)
・四十九日(しじゅうくにち)・七七日(しちしちにち)
・仏飯(ぶっぱん)
・後飾り(あとかざり)
〖霊供膳(りょうくぜん・れいくぜん)〗
『霊供膳』とは、四十九日やお盆,お彼岸,命日などのタイミングで仏壇にお供えする御膳のことです。
『御霊供膳(おりょうぐぜん)』『供養膳(くようぜん)』『仏膳椀(ぶつぜんわん)』もすべて同じ意味。
〖年忌法要(ねんきほうよう)〗
『年忌法要』とは、葬儀後に行う年単位の法要のことです。
一周忌から、3と7のつく年に行い、三十三回忌で終わるとされています。
〖改葬(かいそう)〗
『改葬』とは、お墓に安置している遺骨を別のお墓に移すことをいいます。
〖忌中(きちゅう)・喪中(もちゅう)〗
『忌中』とは、故人が亡くなってから四十九日の法要が終わるまでの期間です。
似ている言葉に『喪中』がありますが、喪中は1年間をいいます。
〖忌明(きあけ)〗
故人が亡くなって、四十九日の法要が終わり『忌中』が明けることを『忌明』と呼びます。
〖初七日(しょなぬか・しょなのか)〗
故人が亡くなって、7日目に行われる法要を『初七日』といいます。
初七日は、故人が三途の川に到着する日とも言われているようです。
〖四十九日(しじゅうくにち)・七七日(しちしちにち)〗
『四十九日』は、故人が亡くなって49日目に行われる法要です。
仏教では、故人が逝去してから49日で成仏されると言われ、忌中の最中に行われる法要のなかで最も重要とされています。
『七七日』も同じ意味です。
〖仏飯(ぶっぱん)〗
『仏飯』とは、仏様に供えるご飯のことをさします。
枕飯とは異なるため、ご飯に箸は立てません。
〖後飾り(あとかざり)〗
『後飾り』とは、火葬が終わり四十九日が終わるまで遺骨などを置く祭壇のことです。
『自宅飾り』『後壇(あとだん)』とも呼ばれています。
読み方だけでも知っておこう!
今回は、葬儀の用語を50個ピックアップしてご紹介しました。
漢字も多く、日常生活では使用しない用語であるため意味はもとより、読み方さえ分からない方もいるでしょう。しかし、基礎的な読み方や意味を知っておくと、スムーズに葬儀や法事の準備ができますよね。
ぜひ参考にしてみてください。