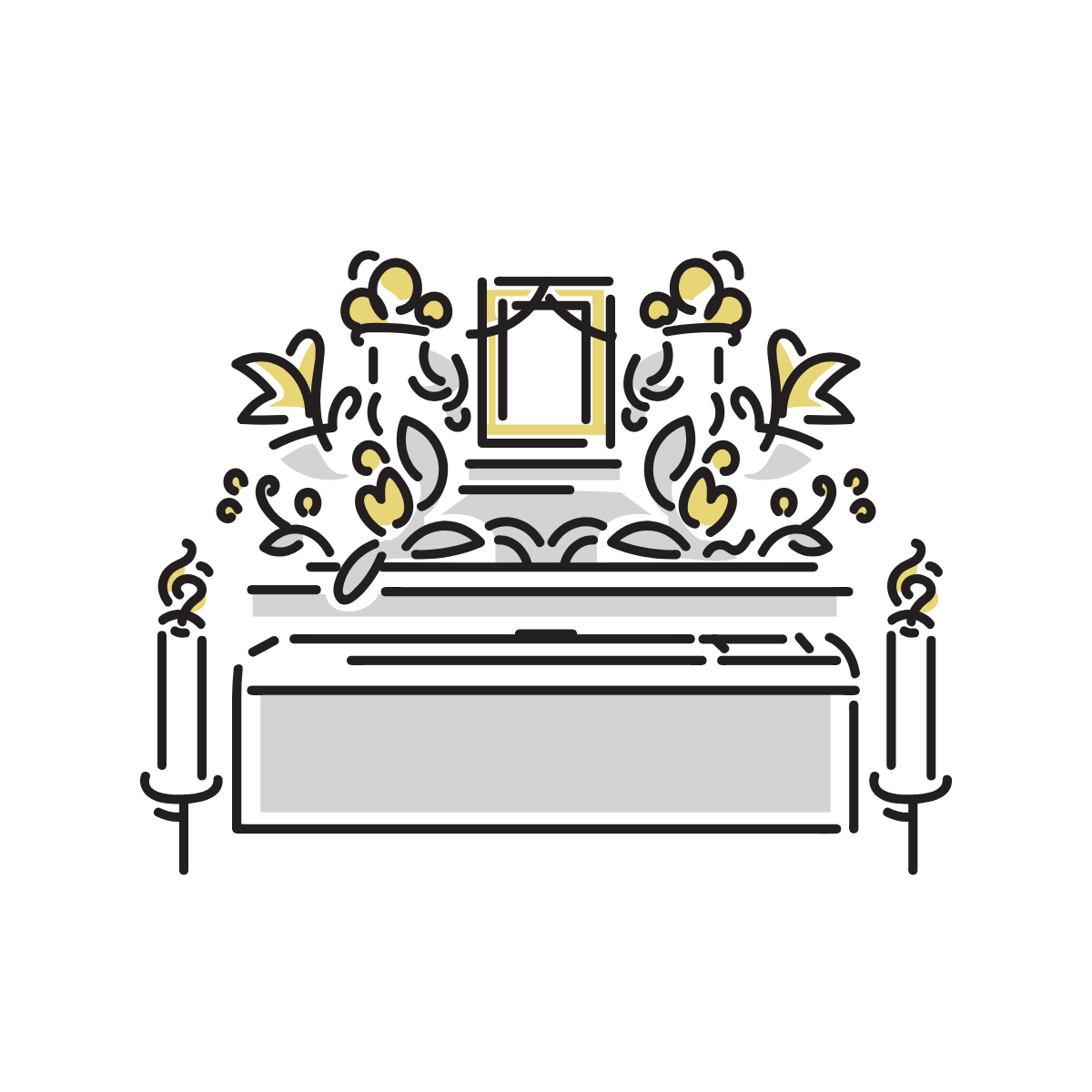【創価学会とは】
創価学会は、日蓮大聖人の説いた仏法を基調とした『平和・文化・教育への貢献』を掲げる団体で、現在は独立した宗教法人として機能しています。
1930年(昭和5年)11月18日に創立され、現在では日本国内に827万世帯(公称)の会員を擁し、日本を含む192カ国に広がる宗教団体です。
創価学会の『創価』とは『価値創造』を意味する言葉です。『万人の幸福』『世界の平和』という価値の創造を実現することを目標としています。
創価学会では、葬儀によって成仏できるのではなく、生前に一生懸命信心することで成仏するのであり、葬儀はすでに成仏した故人に対するものであると考えられています。
そうした考え方にのっとり、1991年ごろより葬儀に僧侶を招かず、故人の友人や在家信者による葬儀が行われるようになり、『友人葬』と称される創価学会独自の葬儀スタイルが確立されました。
〖創価学会の友人葬とは〗
創価学会独自の葬儀スタイルである友人葬とはどういったものなのでしょうか。
○僧侶を呼ばない
友人葬の最大の特徴は、僧侶を呼ばないということでしょう。
葬儀に僧侶を呼ぶようになったのは江戸時代で、檀家制度の始まりとともに普及したものです。『僧侶による引導文の有無や戒名を授けることは、成仏できるかできないかとは無関係である』というのが創価学会の考え方で、形式ではなく『故人を悼むまごころが葬儀において何よりも大切である』『葬儀は故人に対する報恩感謝の念で行われるべきもの』とも説かれています。そのため僧侶は招きません。一般的な葬式の僧侶に代わる人物として、学会員が『導師』として進行役を務めます。学会員の中でも、冠婚葬祭の儀式に通じた幹部(儀典長)が導師を務めることが主流です。
必ずしも生前にお世話になった人が務めるわけではなく、学会の幹部が務めることが多いようです。
創価学会では学会員同士は『友人』と考えることから友人葬と呼ばれています。
導師と参列者一同がともに法華経の『方便品』『寿量品の自我偈』を読誦し、南無妙法蓮華経の題目を唱えます。なお、非会員の方は読経、唱題を行うかどうかは自由です。
○しきみ祭壇を使う
仏式の葬儀に限らず、他の宗教でも花で飾り付けた祭壇が一般的ですが、創価学会の場合はしきみ(樒)を基本にした祭壇になります。
しきみとは、高さ10mほどまで成長し、薄い黄色の花を咲かせる植物です。
根から花まで全てに強い毒性を持ち、強烈な香りを放つのが特徴で、獣や邪気を退けるなどさまざまな効用により、仏事の中で重んじられてきました。
創価学会の友人葬でも花を用いた飾り付けが禁止されているわけではなく、実際に祭壇に花が使われることは珍しくありませんが、厨子に収めて祭壇上部に安置するご本尊の周囲はしきみで飾ると定められています。
○供花にもしきみを使う
供花は遺族が辞退している場合もあるので、送りたい場合は事前に遺族に確認をしましょう。また、供花は祭壇に飾る場合と祭壇とは別の場所に供えるケースがあります。
宗教ごとに贈る花が決められていることもあり、勝手に形式の異なる供花を贈るのはマナー違反になるので注意しましょう。友人葬については、しきみが供花になります。
○戒名を付けない
仏教を開いた釈迦の教えには戒名を授けるという考えはないため、成仏するのに戒名は必要ないというのが創価学会の考え方です。創価学会では成仏するのは死後導いてもらうものではなく、生前の信仰心で決まると考えます。そのため、戒名を付けず、位牌には生前の名前(俗名)が記されます。
○導師への謝礼などは不要
友人葬の名称が示すように、創価学会の葬儀は『遺族と友人によって行われる葬儀』であると捉えられており、導師を務める儀典長も『友人代表』という位置付けです。
そのため、僧侶にお布施を渡す仏式の葬儀とは異なり、導師への謝礼は必要ありません。また、前述のように戒名をつけないので、当然戒名料も発生しません。
○5本房の数珠を用いる
創価学会では日蓮宗・日蓮正宗で用いられる数珠と同じ形式の数珠を使います。片方の親玉から2本の房、もう片方の親玉から3本の房が下がる5本房の数珠を二重にして使います。
非会員であれば、5本房の数珠を用いる必要性はなく、自分の持っている数珠でも問題ありません。
○祭壇の中央上部に本尊を祀る
創価学会で本尊はとても大切で重要とされているので、写真を撮ったり素手で触れたりするのはマナー違反になるので注意しましょう。
【友人葬の流れ】
僧侶を呼ばない、戒名を付けないなどといった特徴のある創価学会のお葬式『友人葬』ですが、式全体の流れは一般的な仏式のお葬式とほぼ同じです。具体的には、以下のような流れとなります。
❶開会の辞
司会者が葬式(葬儀・告別式)の開始を案内します。
❷読経,唱題
導師が中心となり、参列者一同が法華経の方便品を1回、寿量品の自我偈を2回読誦します。また、南無妙法蓮華経の題目を一同で唱題します。
❸焼香
1回目の自我偈に入ると同時に、導師⇨副導師⇨親族⇨参列者の順に焼香を行います。
通常は読経の最中に行います。
❹御祈念文,題目三唱
参列者全員が焼香を済ませたところで導師が合図の鈴を打ち、唱題を終了します。続いて導師により、追善供養の祈念が行われます。合図の鈴に合わせ、参列者一同で題目を3度唱えます。
❺弔慰文,弔電紹介
弔慰文,弔電が紹介されます。学会本部からの弔慰文が読み上げられることもあります。また、導師の挨拶とまとめて行うこともあります。
❻導師挨拶
導師が挨拶を行います。
❼謝辞
喪主(または親族代表)が参列者に対して謝辞を述べます。
❽題目三唱
導師による鈴の合図に合わせ、参列者一同で題目を3度唱和します。
❾閉会の辞
司会者が葬式(葬儀・告別式)の終了を案内します。
❿お別れと出棺
告別式の終了後、導師はじめ参列者一同で題目を唱題しながら、しきみや花などを棺に納め、故人とのお別れをします(お別れの儀式)。
その後、出棺するに当たり、儀典長先導のもと近親者数名(主に男性)で棺を霊柩車まで運びます。出棺に際しては、喪主より挨拶が行われます。
【友人葬の注意点とは】
創価学会のお葬式である友人葬における注意点にはどういったものがあるでしょうか。
○香典辞退の場合が多い
創価学会の方針では、葬式において大切なものは故人の冥福を祈る『まごころ』であり、儀礼的な香典は不要とされています。そのため、一切の香典を受け取らないケースも多いようです。
とはいえ、香典は葬式に掛かる費用の足しにされるという意味合いもあり、香典辞退とする場合はそうした香典収入がなくなることになります。
また、友人葬の場合は親族や友人・知人だけでなく、地域の会員が参列することも想定され、広めの会場を利用することとなり、費用がかさんでしまうことも考えられます。
費用を抑えたい場合には、地域の会員に会葬を控えてもらえるよう、家族葬の形式(基本的に遺族・親族のみで行うスタイル)で葬式を行うなどの旨をあらかじめ周知しておく必要があるでしょう。
また自身が遺族側の場合は、全ての参列者が学会員というわけではないので、香典を持参した方がいる場合はありがたく受け取ります。香典を受け取る場合、香典返しを用意する必要があります。辞退する場合は事前に伝えておくようにしましょう。
基本的に香典は不要と考えられていることから、香典を納める記帳台は設けられていないこともあります。
香典を用意する場合、表書きは『御霊前』または『御香料』と書きましょう。
のし袋には黒白か双銀の水引で結び切りかあわじ結びのものを使います。
○友人葬の実績のある葬儀社を選ぶようにする
全体的な流れは一般的な仏式の葬式と特に違いはないものの、僧侶ではなく導師が儀式を進行することや、しきみ祭壇などといった友人葬特有の部分もあります。そのため、友人葬の実績がない葬儀会社の場合、対応に不備が出てくることも考えられます。安心して手配一切を任せるには、可能な限り友人葬の実績のある葬儀会社に依頼するのがお勧めです。
〖友人葬に掛かる費用とは〗
創価学会の友人葬では、僧侶は呼ばないためお布施は発生せず、導師への謝礼も不要、戒名も付けないので戒名料も要りません。掛かってくる費用は、基本的に実費のみです。
地域差などもあるため一概には言えませんが、直葬だと約20万円~30万円程度、小規模の葬儀だと通夜・葬儀を営むスタイルで70万円程度からが相場と言われています。葬式の規模(=参列者数)により金額は大きく変動するということを念頭に入れておきましょう。
参列者数が多いほど広い会場が必要となるだけでなく、返礼品や会食などの費用もかさみます。その上で香典を辞退するのであれば、香典収入がないという点も計算に入れておく必要があります。
〖友人葬を行った場合の骨上げから納骨について〗
創価学会の友人葬を行った場合、納骨はどのように行われるのでしょうか。
骨上げは一般的な仏式の葬式同様
火葬の前後に導師が中心となって題目を唱えますが、火葬後の骨上げ(遺族や親族の手により遺骨を骨壺に収めること)は一般的な仏式の葬式と同様です。
遺族・親族が2人1組となってそれぞれ箸を持ち、1つのお骨を2人の箸で同時に拾い上げて骨壺に収めます。その際、基本的には血縁関係の濃い順(配偶者は最初)に進めます。
・納骨場所は選択可能
骨壺に収めた遺骨は、公営の墓地などに納骨する他に、遺族の希望によって、創価学会が所有する施設を納骨先として選択することも可能です。
具体的には、創価学会が全国に有する15の墓地公園や、永久収蔵納骨堂、長期収蔵型納骨堂から選べます。
創価学会の学会員がお墓を建てる場合、宗教を問わない墓地・納骨堂や創価学会が運営している墓地・納骨堂から選びます。
仏法の平等観を基調とすることからお墓の形状やデザインは決まっており、墓石の大きさなども全て決められています。
・納骨費用は5万円から
納骨に掛かる費用は、納骨先により異なってきます。
他の骨壺と並べて保管するタイプの永久収蔵納骨堂を選択した場合には、約5万円程度から納骨可能です(納骨後の改葬や分骨などは不可)。
屋内ロッカー型の納骨施設である長期収蔵型納骨堂の場合は、1区画当たり20万円からとなっています。
20年経過後には、遺骨は骨壺ごと永久収蔵納骨堂(常楽納骨堂)へと移して供養されますが、その前であれば改葬や分骨も可能です。
墓地公園に個別の墓を購入する際の費用は、地域によって変わってきます。墓石の大きさは仏教の平等観に基づき一律に定められています。
また、すでに空きのない墓地公園では受付を停止していることもあるので、事前に確認が必要です。
【まとめ】
創価学会では、成仏はあくまで故人の生前の信仰によるとの考え方であり、葬儀の形式ではなく参列者のまごころを重視します。その考えを反映した創価学会の葬式は、「友人葬」と呼ばれ、僧侶を呼ばない代わりに友人の代表として導師が儀式の進行を担い、日常的なお勤めとして励行されている偈文の読誦,題目の唱題が行われます。したがって僧侶へのお布施は発生せず、導師に対しても謝礼などは不要です。
また、創価学会では成仏するのに戒名は要らないという考え方をとっており、位牌には生前の名前が記されるので、戒名料は発生しません。
友人葬の全般的な流れとしては、一般的な仏式の葬儀とおおむね同じですが、香典を辞退する(=香典収入がない)ケースが多いこと、地域の会員が参列することから参列者が多数となる場合も少なくないことに注意が必要です。